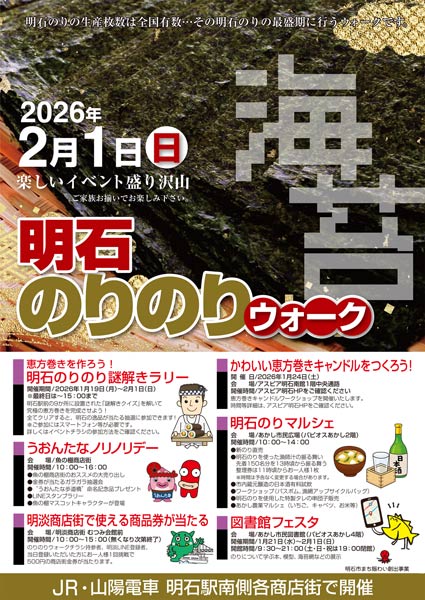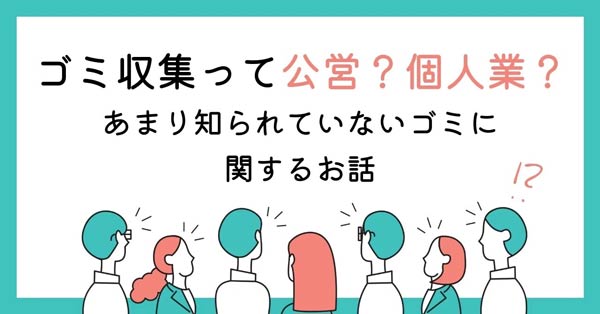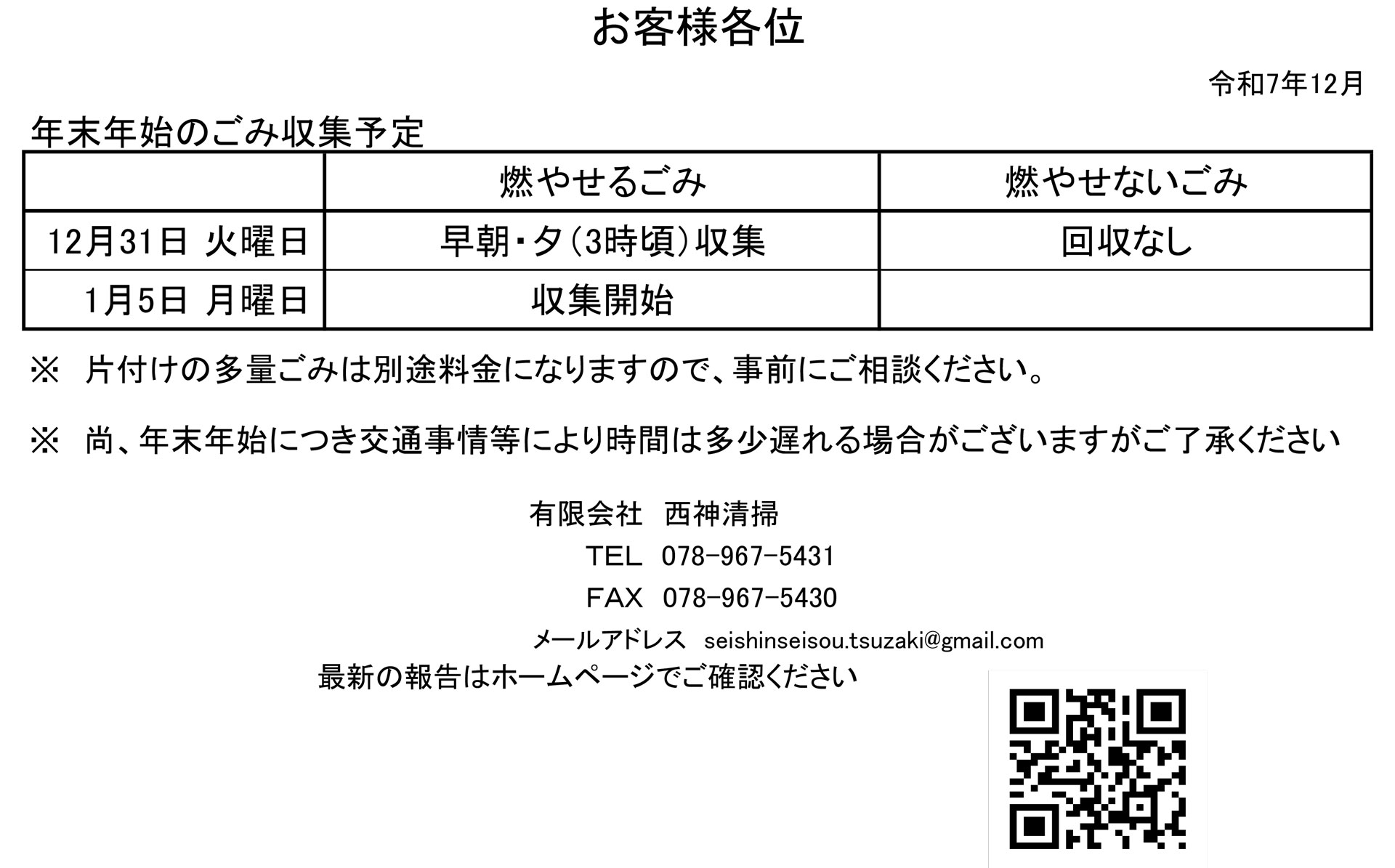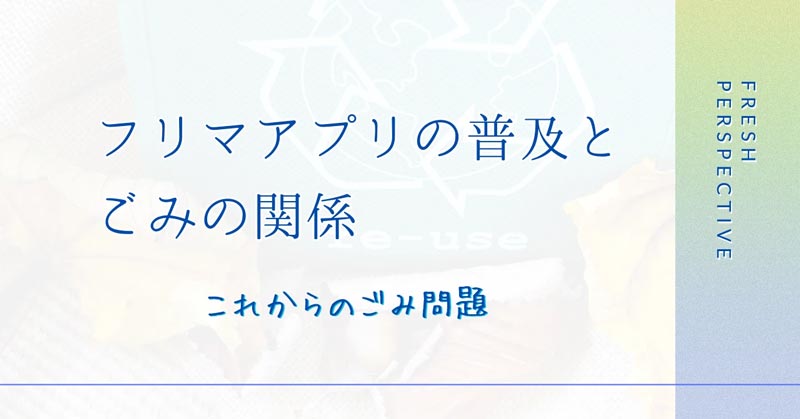
はじめに:フリマアプリと私たちの暮らし
スマートフォン一つで誰でも手軽に不要品を売り買いできる「フリマアプリ」。今や生活に欠かせないツールとして、多くの人が利用しています。メルカリやラクマ、PayPayフリマといったサービスは、単なる売買の場を超えて、私たちの「モノとの付き合い方」に大きな変化をもたらしました。
「使わなくなったから捨てる」のではなく、「まず誰かに譲る・売る」という選択肢が当たり前になりつつあります。これは、ごみ問題や環境負荷の軽減に直結する、重要な社会的変化でもあるのです。
日本のごみ問題と捨てられるモノたち
環境省の統計によれば、日本で年間に排出される一般廃棄物の量は約4,000万トンにも上ります。これは一人当たりに換算すると、1日に約900g。中にはまだ使用可能な家電や衣類、本、家具なども大量に含まれています。
たとえば衣類だけでも、年間約100万トン以上が廃棄され、その多くが焼却処分されています。また、引っ越しや買い替えのタイミングで、状態の良い品がごみとして捨てられるケースも後を絶ちません。
フリマアプリの普及状況と利用実態
では実際に、フリマアプリはどの程度普及しているのでしょうか?
総務省の調査(2023年)によると
- 全体の約40.4%が「フリマアプリを利用したことがある」と回答
- 20代女性では7割以上が利用経験あり
- 若年層だけでなく、30〜40代主婦層にも浸透中
メルカリの発表(2024年3月時点)
- 月間アクティブユーザー数:約2,300万人
- 1日あたりの出品数:100万件以上
- CtoC市場のシェア約9割を占め、日本最大級のマーケットプレイスに成長
こうした数字からも、フリマアプリは一過性の流行ではなく、定着した生活インフラの一部であることが分かります。
再流通がもたらすごみ削減効果
フリマアプリの最大の特徴は、不要品を「ごみ」としてではなく、「資源」として扱える点にあります。
たとえば:
- 子ども服 → サイズアウトしたらすぐ出品。次の家庭へ。
- 書籍 → 読み終えたらまとめて販売。再読される機会が増加。
- 家電製品 → 数回使用後でもニーズあり。リユース市場が活発。
メルカリの報告によれば、2020年時点でメルカリを通じて再利用されたモノの量は年間約50万トン。これは東京ドーム1杯分の廃棄物量に相当し、ごみとして廃棄されていたはずのモノたちが、新たな持ち主のもとで再び活用されているのです。
フリマアプリの課題と新たな視点
とはいえ、フリマアプリには課題もあります。
主な課題
- 配送によるCO₂排出の増加
- 過剰包装やプラスチックごみの発生
- 中古品の品質やトラブルへの不安
- “売れればいい”という姿勢による不要品の押し付け(実質的な不法投棄)
フリマアプリの利用を「エコ」な行動として持続可能にするには、出品者・購入者のモラルや意識の向上とともに、アプリ側の環境配慮機能(梱包ガイド、エコ配送、リサイクル支援など)の整備が求められています。
一人ひとりの行動が社会を変える
フリマアプリは、「手放す=捨てる」から「手放す=つなぐ」へと、私たちの意識を変えてくれました。
再流通は、ごみを減らすだけでなく、モノの命を延ばし、人と人とをつなぐ仕組みでもあります。
家の中の不要なモノも、誰かにとっては「欲しいモノ」かもしれません。
「売ってみる」という一歩が、循環型社会の構築につながります。
まずは1品から、フリマアプリを通じてモノを手放してみませんか?
SNSはこちら
粗大ゴミや大型ゴミ、不用品など、ゴミのお困り事は西神清掃へ