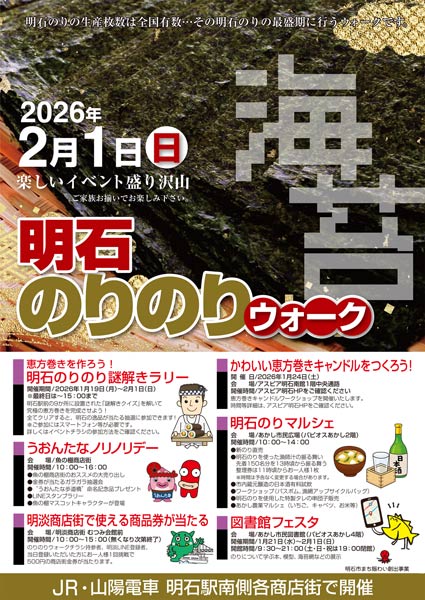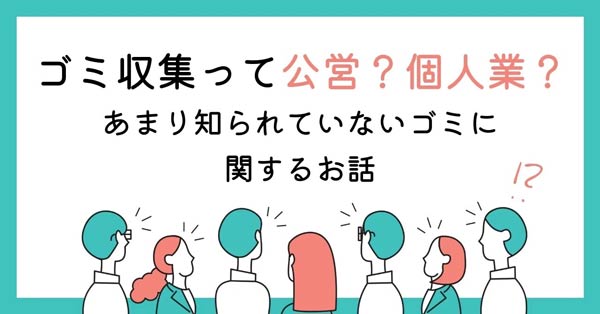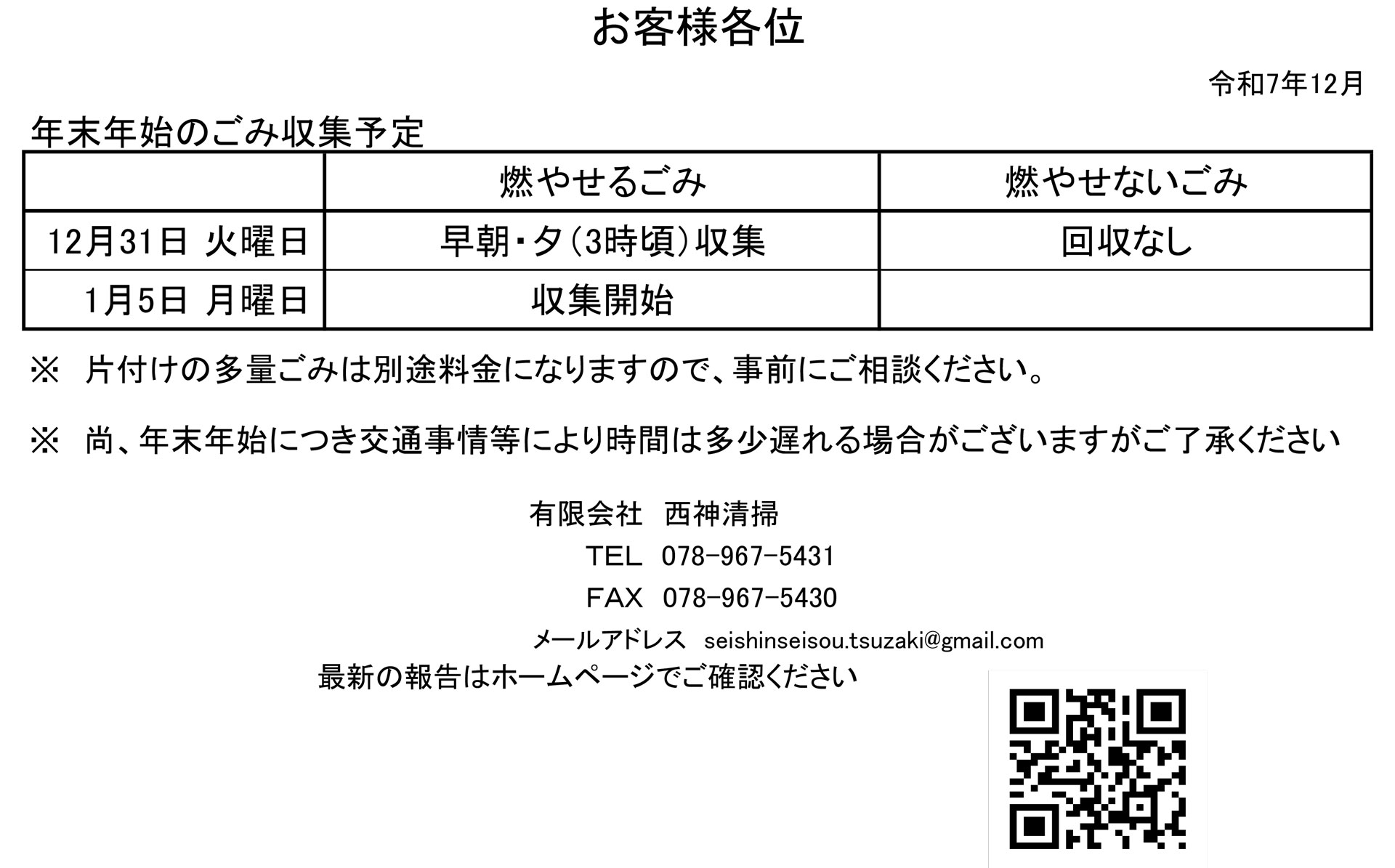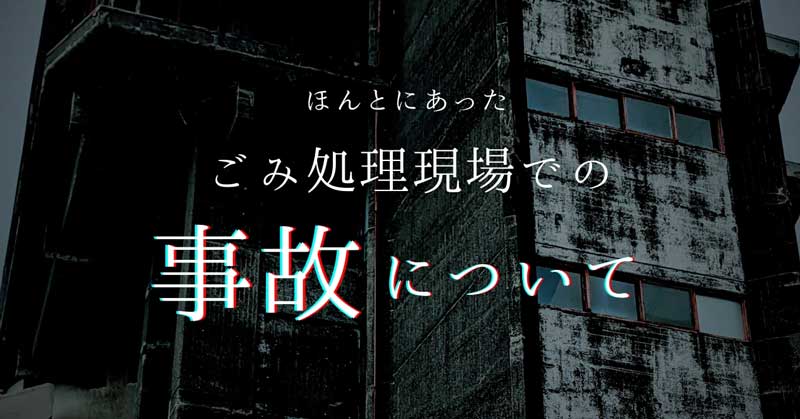
目次
はじめに
日々の生活で出るごみの中には、適切に処理しないと火災やケガの原因となるものがあります。実際、ごみ収集や処理の現場では、火災や事故が頻繁に発生しており、安全なごみ出しが求められています。今回は、火災やケガの事例を紹介しながら、どのような点に気をつけるべきか解説します。
ごみ処理現場で発生する火災の事例
リチウムイオン電池の発火
スマートフォンやモバイルバッテリー、ノートパソコンなどに使用されるリチウムイオン電池は、ごみ収集車や処理施設で圧縮・破砕される際にショートを起こし、火災の原因となることがあります。
事例:
- 2023年、東京都内の清掃工場で、リチウム電池が原因とみられる火災が発生し、一時操業停止。
- 2022年、大阪府のごみ収集車内で火花が発生し、火災に至る事故が発生。
対策:
- リチウムイオン電池は自治体指定の方法で回収ボックスなどに出す。
- 破損したバッテリーは絶縁テープで端子を保護し、安全に処理する。
スプレー缶・カセットボンベの爆発
スプレー缶やカセットボンベのガスが残ったまま処理されると、破砕機で火花が発生し、爆発・火災につながることがあります。
事例:
- 北海道の廃棄物処理施設でスプレー缶の爆発が発生し、施設の一部が焼損。
対策:
- 中身を完全に使い切り、風通しの良い場所で穴を開ける(自治体のルールに従う)。
- 専用の回収ボックスを利用する。
可燃物の自然発火
布製品(衣類やタオル)に含まれる油分が酸化し、自然発火することがあります。
事例:
- 兵庫県のリサイクル施設で、洗濯後のウェスが自己発熱し、火災が発生。
対策:
- 油のついた布類はしっかり乾燥させてから捨てる。
- 可能な場合は可燃ごみではなく産業廃棄物として処理する。
ごみ収集作業員が遭遇するケガの事例
針・刃物による負傷
ごみ袋に直接、割れたガラスやカミソリ、注射針などを捨てると、作業員が手を傷つける危険があります。
事例:
- 名古屋市で、回収作業中の作業員が誤って医療用注射針を刺し、病院で治療。
対策:
- 割れたガラスや刃物は新聞紙などで包み、「危険」と明記。
- 注射針は自治体の指定方法で処理。
重量物の落下事故
家電や家具などの粗大ごみが崩れ、作業員が下敷きになる事故も発生しています。
事例:
- 東京都の粗大ごみ処理場で、作業員が倒れてきた冷蔵庫に挟まれ骨折。
対策:
- 重量物は分解できるものはできるだけ小さくして処理する。
- 回収時に安定した状態で出す。
有害ガスによる中毒
塩素系洗剤と酸性洗剤が混ざると、有害な塩素ガスが発生することがあります。
事例:
- 京都府の廃棄物処理場で、異物混入による化学反応で有毒ガスが発生し、作業員数名が病院搬送。
対策:
- 洗剤類は種類ごとに分けて処分。
- できるだけ使い切ってから捨てる。
安全なごみの出し方
ごみを出す際に、以下の点に注意すると事故のリスクを減らせます。
- 危険物は適切に処理する
- リチウム電池、スプレー缶、化学物質などは自治体の指示に従い処理。
- 鋭利なものは包んで出す
- 割れたガラスや刃物は新聞紙などに包み、「危険」と表示。
- 重いごみは安定させる
- 家具・家電は倒れないように配置し、分解できるものはできるだけ小さくする。
- 分別を徹底する
- プラスチック・燃えるごみ・リサイクルごみなどのルールを守ることで、異物混入による事故を防ぐ。
- 収集時間・方法を守る
- 指定時間外のごみ出しは、火災や散乱の原因となるため、ルールを遵守する。
まとめ
ごみ処理は日常生活に欠かせない活動ですが、不適切なごみの出し方が火災やケガの原因となることがあります。リチウム電池やスプレー缶などの危険物の処理方法を守り、鋭利なものを適切に処理することで、事故を未然に防ぐことが可能です。安全で快適な街づくりのために、私たち一人ひとりが責任を持ってごみを出しましょう!